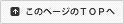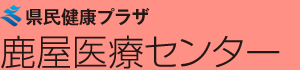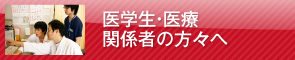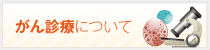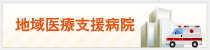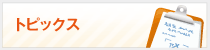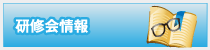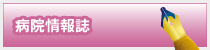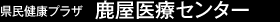臨床倫理指針
県民健康プラザ鹿屋医療センター臨床倫理指針
I.基本指針
- 患者さんの人格を尊重し,公平かつ公正な医療を行います。
- 患者さんの意思を尊重し,患者さんが治療を選択できるよう十分な情報を提供して説明し,理解と同意に基づいて医療を行います。
(1) 判断能力が欠如している患者さんへの対応
適切な代理人に説明し,理解と同意を得ます。
適切な代理人がいない場合は,担当医の判断を基に,臨床倫理委員会で方針を決定します。
(2) 宗教上,治療が制限される患者さんへの対応
当院の「『輸血を拒否する患者さんへの施術』の取り扱い」に基づき判断します。
(3) 当院ではいかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助は認めません。
- 医学的適応を確認し,患者さんにとって最善で最良の医療を選択して,リスクを最小限に留め,最大の利益がもたらされるよう努めます。
ただし,治療によるリスクと利益を提示し,その上で患者さんが望まない治療を拒否できる権利を認めます。
なお,感染症法など法に基づく措置が必要な場合は,治療を拒否できる権利は制限されます。
- 国や学会等の関係法令やガイドラインを尊重し,安全で信頼される医療を行います。
- 患者さんの生活の質(QOL)を考慮した医療を行います。
- 医療発展のために必要な臨床研究は,臨床倫理委員会や生命倫理委員会で決定した指針等に基づいて行います。
II.主な臨床倫理問題の指針
- 新しい医療技術の導入
国や学会等の指針やガイドライン,治験及び調査研究等審査委員会や生命倫理委員会で決定した指針等に基づいて行います。
- 研究実施の判断
国や学会等の指針やガイドライン,治験及び調査研究等審査委員会や生命倫理委員会で決定した指針等に基づいて行います。
- 終末期医療
根治目的の治療から代替治療・緩和ケアへの段階的移行は,「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(H19年,厚労省)」を参考に,医療行為の妥当性を十分 に考慮し,患者さんや家族等に説明し,理解と同意を得て開始します。
また,心肺蘇生やDNARについて患者さんや家族等に説明し,心肺蘇生の意思を確認します。
(1) 患者さんが意思表示できる間に,延命治療など終末期医療に対する意思を確認し,これを重視します。
(2) 患者さんの意思が確認できない場合で,家族等から患者さんの意思が推定できる場合は,これを重視します。
(3) 患者さんの意思が確認も推定もできない場合で,家族等との話合いで意見の一致があれば,これを重視します。
(4) 患者さんの意思が確認も推定もできない場合で,家族等との話合いで意見に一致がみられなければ,担当医の判断を基に臨床倫理委員会で方針を決定します。
- 身体抑制等
治療上身体抑制が必要な場合は,当院の医療安全対策マニュアルに従い,患者さんや家族等に説明し,同意を得て行います。
また,身体抑制中は頻回に状態を観察し,身体抑制は必要最軽・最短期間とします。
- 職業倫理指針
(1) 医療従事者としての責任,義務,使命を自覚し,教養や人格を高めるように努めます。
(2) 医療の知識や技術の向上に努め,最良の医療が提供できるように努めます。
(3) 患者さんのプライバシーを尊重し,診療における個人情報の保護と守秘義務を遵守します。
(4) 医療従事者としての専門性を互いに尊重し,チーム医療や医療連携を推進します。
(5) 県立病院の職員として,公共性を重視し,医療を通して地域の発展に貢献します。